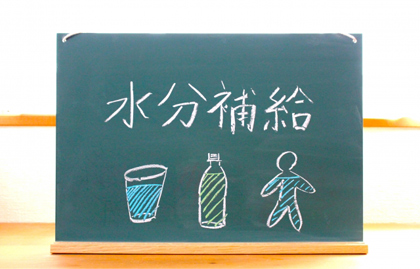スポーツで起こりやすい怪我の対処法と準備運動のアドバイス

スポーツを安心して楽しむためには、怪我の予防と適切な対処法を知っておくことが重要です。スポーツを安全に楽しむための怪我の対処法と効果的な準備運動などについて医師に伺いました。
スポーツでの怪我にはどんなものがある? スポーツ傷害とは違うの?
Q. スポーツでの怪我とスポーツ傷害は違うのですか?
A.
いわゆるスポーツでの怪我は、専門用語では「
Q. スポーツ外傷には、例えばどんなものがありますか?
A. 代表的なスポーツ外傷には、関節の脱臼や捻挫、骨折、肉離れなどがあります。
Q. スポーツ外傷の起こりやすい競技などはありますか?
A. 全てのスポーツに外傷のリスクがありますが、とくに柔道やラグビー、サッカー、バスケットボールなどの激しいコンタクトスポーツでは外傷のリスクが高いと言えると思います。また、それぞれのスポーツに特徴的な外傷というのもあります。
Q. どんなスポーツにどんな外傷が多くみられるのですか?
A. 例えば柔道でしたら、技をかけたりかけられたりする際の肩・膝関節の脱臼や捻挫、突き指など、サッカーでしたら、人との激しい接触によって打撲や骨折が起こったり、全力でキックした時に空振りするだけで靭帯を痛めたりすることあります。ほかにも股関節、膝関節、足関節の捻挫、肉離れ、腰の怪我が多くみられます。また、バスケットボールの怪我として、ボールを取り合う際、パスカット時の指の捻挫や脱臼、ジャンプをする時、ピボット時の膝や足首、腰痛など全身のどこにも怪我をする危険があります。ジャンプや着地による膝や足首の靭帯の断裂もとても多いですね。
スポーツで起こりやすい怪我の対処法を教えて!
Q. 怪我をした場合、どう対処したら良いのでしょうか?
A. まずは速やかに競技から離れ、安静にすることが大事だと思います。基本的な応急処置としては、冷却、固定し、腫れている場合は怪我をした部位が心臓より高い位置に来るようにしましょう。明らかに「いつもと違う」と感じた場合は、様子を見ず、専門の医療機関などを受診した方が良いと思います。
Q. そうなのですね。
A. とくに「脱臼」の際は自己流で戻そうとするのはやめましょう。 脱臼は、関節が外れた状態のことを指し、肩・肘・指などでよく発症します。外見上、見たことのない独特な変形を起こし、徐々に腫れや痛みが出現してくるのですぐにわかるかと思います。一度脱臼した部分は再び脱臼しやすくなることが多いようなので、少しでも早く適切な整復処置が必要です。
Q. 捻挫などの場合はどうですか?
A. 安静にし、できるだけその部位を圧迫、固定することが大事です。捻挫は足首や膝関節に起こりやすく、関節に過度の負荷がかかり、靭帯を損傷してしまった状態です。つき指などもここに分類されます。捻挫は放置してしまうと治りが遅いばかりか、関節を庇うことで周りの筋肉が固くなり、生活に支障をきたす恐れがあります。また、脱臼などと同様に「クセになる」ことも多いので、早急処置のあとは速やかに専門家に診てもらいましょう。
安心してスポーツを楽しむためのアドバイスを教えて!
Q. できるだけ怪我の心配をせず、安心してスポーツを楽しむにはどうしたらいいですか?
A. 大事なのは準備運動だと思います。とくにスポーツをおこなう前にお勧めなのがダイナミックストレッチと呼ばれるストレッチです。これは寝たり座ったりしておこなうストレッチ(普段皆さんおこなっているストレッチ、正式にはスタスティックストレッチという)ではなく、徐々にその競技の動きに近付けながらおこなうストレッチです。サッカーの場合であれば「ブラジル体操」、野球であれば短い距離からおこなうキャッチボールなどがダイナミックストレッチにあたります。また、私の見解としては、翌日以降に筋疲労などを蓄積させないためにも、運動後のアイシングやストレッチ、入浴や疲労回復系のサプリメントも取り入れるといいと思います。
Q. ほかには何かありますか?
A. 整骨院などで、定期的なチェックをするのがお勧めです。スポーツ外傷だけでなく、先述の使い過ぎや同じ動作を繰り返しおこなうことで生じる「スポーツ障害」の予防や早期発見にも非常に有用です。

髙橋 弘(はざま鍼灸整骨院)
東京医療専門学校(現・東京呉竹医療専門学校)柔道整復科卒業後、国家資格「柔道整復師」を取得、その後、同鍼灸科を卒業し国家資格「はり師 きゅう師」取得。2004年専門学校の講師の傍ら、自身の地元に「はざま鍼灸整骨院」を開業し、現在に至る。
引用:「Medical DOC(メディカルドック) - 医療メディア」より
※記事内容は執筆時点のものです。
免責事項(Medical DOCサイトへ)
このコラムを読んだ方におすすめのアプリ